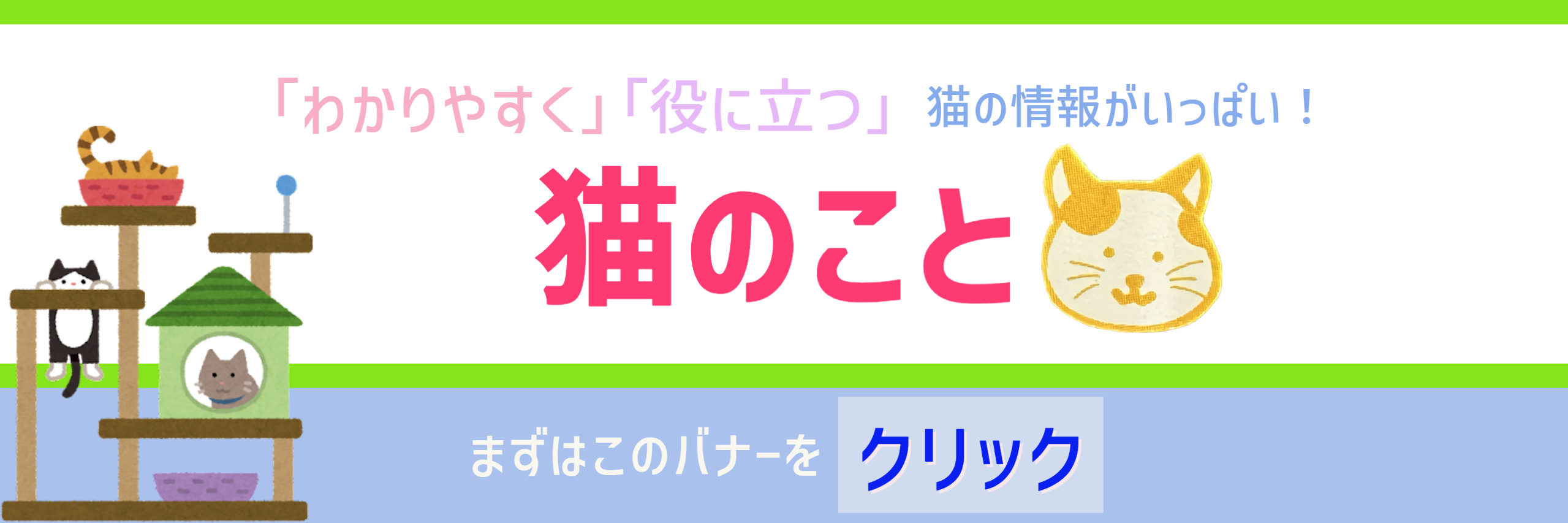当院では先月からSDMA値を院内で測定できるようになりました。
SDMA値を測定するために今までは…
採血して血清サンプルを作成して検査センターにそれを送付して、数日後に結果報告が来る
要するに、
検査結果が分かるまでにけっこう時間がかかっていましたが、
院内で測定できるようになったので
他の検査結果とともにSDMA値の結果がすぐにわかるようになりました。

↑当院ではアークレイ社の免疫反応測定装置 Vcheck V200を導入しました。フジフィルム社の免疫反応測定装置では測定できない項目も測定できたりします。検体の希釈を自分でしなければいけない手間はかかるのですが慣れれば大した問題ではないかなと思います。
ということで、
今回は猫とSDMAのことを思いつくままに書いていきたいと思います。
~個人的見解をけっこう含むだけでなく、学術的な内容でないところも多々あります~
①SDMAとは?
対称性ジメチルアルギニンのことです。
英語で書くとSymmetric DiMethylArginineです。
②えっ!?それだけ?
SDMA=対称性ジメチルアルギニン
以上で説明終了
なんぼいうてもそりゃないだろう
ということで、
もう少しちゃんと書きます。
③糸球体濾過という重要な働き
SDMAを考える上で、どうしても切り離せない腎臓の働きについて最初にかんたんに書きます。
生体内で腎臓がしている働き(=仕事)は細かいものも含めるとたくさんあります。
~その全部をここで紹介することはしません→気になる方はGoogle様やChatGPT様に聞いてみてください~
そのたくさんある中で本業と言えるだろう仕事に尿を作る仕事があります。
少し具体的に言うと…
腎臓の中にある糸球体という濾過装置を用いて血液をジャンジャン濾過して尿(原尿)を作る仕事です。
血液を濾過することによって体の中の余分なものを排出しています。
~ちなみに、濾過した後「やっぱ必要なもの」は再吸収しています~
~こうすることで体内の水分量などを調節しています~
もしも、
腎臓が様々な事情(≒疾患)で仕事をあまりしなくなると…
~腎臓が仕事しない≒腎機能が低下~
濾過量が減ってしまいます。
つまり、
腎機能が低下すると、糸球体濾過量が減る
ことになります。
ってことは…
逆に考えると、
糸球体濾過量が減っているかどうか?を調べることで腎機能が低下しているのかどうかを評価できます。
その糸球体濾過量の指標としてSDMAを測定します。
SDMAはタンパク質が体内でゴニョゴニョっと(詳しくは割愛)変化してできた産物です。
SDMAの大部分は糸球体で濾過されて、いらない物として体外に排出されます。
しかし、
腎機能が低下して糸球体濾過量が減ってくると、血液中に残ってしまいます。
~血中SDMA濃度は糸球体濾過量に依存しています~
なので、
血中のSDMA濃度を測定してみて値が高い=糸球体濾過量が減っている=腎機能が低下している
と推定できます。
④クレアチニンでもいいんじゃない?
腎機能を評価する上で昔からよく使われる指標にクレアチニンがあります。
ほとんどの動物病院ですぐに数値を出せるという点で簡便性に優れた指標となります。
オーナー様においても当たり前に聞いたことがある血液検査項目だと思います。
~腎臓といえばクレアチニンという感じに知れわたっている気がします~
これだけ一般に普及したクレアチニンなので、
「クレアチニンだけ測定すればいいんじゃないの?」
「なんでSDMAまで測定する必要があるの?」
「余分に費用をかけてまでSDMAを測定する意味あるの?」
と思うオーナー様もいらっしゃると思います。
たしかに、
血中クレアチニン濃度もSDMAと同様に糸球体濾過量に依存しています。
糸球体濾過量が低下すれば血中クレアチニン濃度があがります。
糸球体濾過量から腎機能を推定する点ではクレアチニンもSDMAもいっしょです。
「やっぱどっちも変わんないじゃん」
「クレアチニンだけでいいじゃん」
「やっぱSDMAなんて過剰な検査なんじゃないの?」
という声も聞こえてきそうですが、
どっちも変わんないならSDMA測定が猫慢性腎臓病界隈でクローズアップされるようにはなりません。
SDMAにはクレアチニンよりも優れたところがあります。
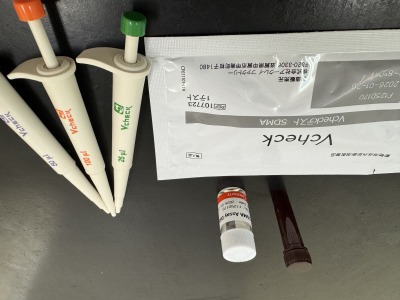
↑Vcheck V200でSDMAを測定するためのキット。測定するまでの前処理行程が多くなっています。3種類のオートピペットを用意して、除タンパクして、遠心かけて、さらに希釈して、さらにタブレット試薬を溶かしてみたいな感じです。ここまで全部自分でする必要があります。前処理が終われば測定自体は5分で終わります。前処理の時間の方が全然かかります。大学の時は生化学研究室にいたのでその時のことを思い出しました。SDMA単体で測定できるのはいい点です。
SDMAのいいとこ1つ目
⑤腎臓病の早期発見に有用?
まずは、
教科書的な一般論を書きますが…
Cre値は腎機能が75%低下するまで上昇しません。
~Creが上昇してきたな!とわかった頃には腎機能の余力はもう25%程度しかありません~
それに比べて、
SDMAの数値は腎機能が平均40%低下すると上昇すると言われています。
~25%腎機能が低下したら上昇することもあるようです~
このことから、
SDMAは腎機能の低下を早期に発見できるかも?
ということになります。
ただ、
「40%低下がどうのこうの」
「75%低下がどうのこうの」
と言ったところでオーナー様にはピン!とこないと思うのでもっとわかりやすく説明します。
(例えが悪いかもしれませんが…)
Cre→腎機能が75%低下して初めて腎臓の異変を知らせてくれるということは…
火災で家が焼け落ちて基礎と柱だけ残っているような段階で
「火事ですよ!」
と知らせるようなものです。
「そこまでいく前に早く教えてくれよ!遅すぎるよ!」
となります。
その一方、
SDMA→腎機能が40%低下して初めて腎臓の異変を知らせてくれるということは…
火災で家からケムリがあがったor最悪、炎が見えた段階で
「火事ですよ!」
と知らせるようなものです。
家のダメージ、その後の消火活動を考えるとどちらがよいのかは言うまでもありません。
繰り返しになりますが、
CreとSDMAの違いを少し大袈裟に言うと
焼け落ちて基礎と柱だけになってから火災を教えてくれるのか?=Cre
それとも、
ケムリがあがった段階で火災を教えてくれるのか?=SDMA
こういう違いになります。
SDMAのいいとこ2つ目
⑥筋肉量に左右されにくい
そもそも、
Creは筋肉が代謝されることによってできる物質なので
当たり前ですが、
筋肉が多いほどその絶対量は多くなるし
筋肉が少ないほどその絶対量は少なくなります。
ということは、
やせ細って筋肉量が少ないと腎機能が低下したとしてあんまりCre値は上昇してきません。
~やせているとそもそものCreの絶対量が少ないからです~
要するに、
普通体型の猫のCre=1.5mg/dlとガリガリに痩せた猫のCre=1.5mg/dlは全く解釈が違う!ということです。
~ガリガリに痩せた猫のCre=1.5mg/dlは筋肉が少ないからCreが上がってないだけでその数値を額面通り受け止められません~
このように、
筋肉量に左右されるのがCreの欠点になります。
~人間では(筋肉量の違いを考慮して)性別や年齢によってCreの基準値は変わってきます~
それに比べ、
SDMAは全身の様々な細胞でできる物質なので筋肉量の影響を受けにくいとされています。
標準体型の猫でもガリガリに痩せた猫でもある程度同じ尺度で数値を扱うことができます。
なので、
普通体型の猫のSDMA=16μg/dlとガリガリに痩せた猫のSDMA=16μg/dlを(ある程度)同じように解釈できる!
ことになります。
高齢でやせ細った猫の腎機能を評価しようとするならばSDMAを測定するほうがベターかなと思います。
⑦すげぇじゃん!SDMA
ここまでで…
・SDMAの教科書的ないいとこ
・SDMAの理論的な優位性
・SDMAワッショイ♪ワッショイ♪
を書いてきたので
「これはすごい、これからは絶対SDMAも検査しよう♪」
「これからはCreじゃなくてSDMAで腎臓病を早期発見しよう♪」
「クレアチニンよ、さらば!」
すげぇじゃん!SDMA!
とオーナー様は思ったかもしれません。
~いいとこばかりをピックアップするとそう思われても仕方ありません~
(そんなオーナー様に対して)
ここでハッキリ私の意見を書いておきますが、
SDMAはそんなにすごいものではありません!
Creにとってかわるものではないし、万能でもありません!
SDMA単独で慢性腎臓病を早期発見・診断できるなんてことはありません。
あくまで、
猫の腎臓病の診断を助けてくれる検査の中の1つに過ぎません。
ここからはディープな個人的見解をどんどん書いていきます。
⑧ふわっとしたSDMA
SDMA値は経験上いろいろな要因でけっこう動くような感触がします。
ある日測定したら10μg/dl、数時間後に測定したら12μg/dlってこともあります。
~いわゆる日内変動~
多分、
・同一検体をフジフィルム様、アイデックス様に測定依頼しても
・同一検体をアークレイ様の院内マシン、アイデックス様の院内マシンで測定しても
SDMAの値は多少違うんじゃないかなと思います。
~まぁ、こういうことはSDMAに限ったことではないのですが~
Creの値はそこまで値がばらける印象がありません。
様々なな報告や発表を見ると、
たしかにSDMA値は様々な要因で変動しやすいようです。
学問やエビデンス度外視のもう完全な私見、感覚の話ですが、
SDMA値はふわっふわしている気がします。
まさに、一時期ブームになったおいしいパンケーキです。
それに比べてCre値はもう少しカチッと硬めな気がして…
昔ながらの定番ホットケーキです。
~まぁ、どちらにせよ「あずきバー」まではいかないのですが…~
⑨CreとSDMAの関係性
「Creの値がけっこう上がっているのにSDMAの値はそれほど劇高ではないなぁ」
「Creの値は徐々に上昇傾向なのにSDMAの値はなんかなぁ」
ってことがよくあります。
慢性腎臓病の進行や改善にCre値は素直に反応していると感じるのに対してSDMA値は素直ではないなぁという私の印象です。
SDMAの値をどのように扱いどう解釈するのかを悩むことがあります。
そこそこの頻度で、
クレアチニン値とSDMA値を見比べた時の違和感
を感じることがあります。
➉SDMA単独でどうこう言うのは無理
値の変動のこと、パンケーキっぽさを考えると…
SDMAを単回・単独で測定してどうのこうの判断することは無理
と私は考えています。
(Cre値は基準範囲内だけど)
「SDMA=17μg/dlってだけで腎臓病の治療や療法食を始めましょう」
というのはやや乱暴かなと思います。
そもそも、
慢性腎臓病というのは「慢性」じゃないと診断できないので
たった一度の検査で慢性腎臓病と診断することはあまりよくないと考えられています。
⑪結局、SDMAってどうなの?
(なんやかんや好き勝手放題書いているけど)
「SDMAって結局どうなの?結局いいのかわるいのかわからんよ」
「実際どういう時にSDMAは役に立つの?」
こんなオーナー様の疑問の答えを最後に書いていきます。
(1)SDMAは足がかりに過ぎない
猫の診療を続けていると…
定期的な検査によって腎臓の状態をモニタリングしているけれども
・Cre値が1.5mg/dlをずっと前後していてほとんど変わりない
・臨床症状もあまりないし、尿検査・身体検査所見もそれほど悪くない
ってことがあります。
~この状態が年単位で続くこともあります~
こんな時にSDMA値が力を発揮することがあります。
具体的に書くと…
Cre値が1.5mg/dl前後をうろちょろ→SDMA値も10~12μg/dl前後をうろちょろ
であれば「これまで通りの経過観察にしましょうか?」になりますが、
Cre値が1.5mg/dl前後をずっとうろちょろ→SDMA値は14μg/dl前後をうろちょろしながら
場合によっては、
→徐々に16μg/dlから18μg/dlに向けて上昇傾向
こんな風になってくると、
「ん?なにかあるかもな」
ということで、
「慢性腎臓病の可能性も否定できないので、もう一歩踏み出した検査もして総合的に判断しましょうか?」
という提案をオーナー様にします。
ここでオーナー様に誤解して欲しくないのは
SDMAが高いってだけで慢性腎臓病ではないし
SDMAが高いってだけで治療開始ではない
ということです。
~繰り返しにはなりますが~
なぜならば、
診断・治療は常にその他所見も合わせた総合判断が必要であるから
ってことは当然として、
前述した通り、SDMA値には変動や腎臓以外の要因での上昇があるからです。
~SDMAはそれだけで診断できるほど大それたものではないということです~
~仮に持続的なSDMA値上昇があったとしても、それだけで診断できるほどのものではありません~
SDMA値のフワフワ感を考えるとその値だけでの診断は不可能です。
ただ、
慢性腎臓病を早期発見する足がかりを作ってくれる!
ことは間違いありません。
定期的にCreだけでなくSDMAも測定してるからこそ気付けることが確実にあります!
だからこそ、
オーナー様の了承をいたたければ、日常の健康診断でSDMAも測定しています。
(2)筋肉量が少ない猫
たとえば、
それほど削痩していない猫が初診で来院して血液検査をしてみたらCre値がかなり高かった
こんな時にSDMAも測定しておいた方がよいのかというと、必ずしもSDMAまで測定しなくてもよいと私は考えます。
~すでにCreが高い削痩してない猫に対してSDMAをあえて測定する意義は少ないと私は考えています~
では、
かなり削痩した年老いた猫が初診で来院して血液検査をしてみたらCre値が高かった
こんな時はどうでしょうか?
SDMAを測定してみるのも悪くはないかなと思います。
削痩しているのでCre値を過少評価しているかもしれないからです。
削痩して筋肉の少ない猫においてCreの評価を補完してくれることがSDMAのいいところです。
しかしながら、
Cre値の高い削痩した老猫のSDMAをあえて測定したところで、その後の対応や治療が大きく変わるわけではない
と私は思うので、
そういう時にSDMAまで測定することにたいした意味はないかなとも私は思います。
もしも、
かなり削痩した年老いた猫が初診で来院して血液検査をしてみたらCreの数値がギリ基準範囲内だった
というのであれば、
臨床症状やその他の所見も考慮した上でSDMAも測定してみる
ってことは有意義だと思います。
⑫まとめ
病気の診断・治療をする時にいろいろな面から診てみるというのは大切だと思います。
そのいろいろな面の1つにSDMAが存在します。
あくまで、
診断材料の1つに過ぎないのがSDMAです。
身体検査、血圧、尿比重、画像診断、尿検査、Cre値…etc
こんな各種検査(≒診断材料)のなかの1つに過ぎないのがSDMAです。
とはいえ、
SDMAはその値の解釈や使い方を間違わなければとても魅力的な指標だと思います。
その最大の魅力は、
健康な時から定期的に測定することで腎臓病を早期発見する足がかりになる
~腎臓病以外の疾患も早期発見できる可能性もあります~
ってことだと私は考えています。
SDMA=足がかり
であって、
猫の慢性腎臓病のステージングにあえてSDMAを使う意義はそれほどないかな
~たとえ、筋肉量に左右されにくいメリットがあったとしても~
~削痩してようがなかろうが、すでにCreがガンガン上がった猫のSDMAを定期的に測定する意義はたいしてないと私は考えます~
というのが私の見解です。
~一次診療の臨床医という立場からの見解です~
(この記事を読んだ上で)
SDMAについての相談、猫の慢性腎臓病の診断治療のために当院を受診していただく場合は必ず副院長を指名していただきますようお願いいたします。